- ホーム
- PFAS汚染対策サービス
- 一般知識
PFAS関連の一般知識
PFASには撥水性や耐熱性などの優れた特徴がありさまざまな用途で使われていますが、健康や環境への悪影響が明らかになるに従い、世界中で規制が強化されています。日本でも環境省がPFAS関連物質の監視体制を強化しており、法規制が進むと予想されます。自治体や企業においては、詳細な調査や対策の検討が必要になってくると思われます。
※ このページは、2025年2月現在の情報に基づいて記載されています。

PFASとは何か
PFASの特徴
PFAS(ペルフルオロアルキルおよびポリフルオロアルキル化合物)とは、有機フッ素化合物の総称で、炭素-フッ素結合を持つことが特徴です。この結合は非常に強固で、化学的にも物理的にも安定しています。そのため、PFASは高い耐熱性、耐薬品性、防水性、防汚性を有しています。一方、PFASは生分解されにくく、環境中に長期間残留することから「永遠の化学物質」とも呼ばれています。
PFASは、長鎖と短鎖のものがあり、代表的な長鎖PFASにPFOA(ペルフルオロオクタン酸)やPFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)が含まれます。なお、課題が指摘されて規制の検討対象となっている物質は、PFAS全体のうちの3種類(PFOS、PFOA、PFHxS)です。
PFASの使用用途
PFASはその優れた特性から、以下のようなさまざまな製品や用途で使用されています。
生活用品
- 防水・防汚加工を施した衣類、カーペット、家具などのテキスタイル製品として
- 耐熱性材料としてのクッキングペーパーや食品包装材、焦げ付き防止調理器具のコーティング剤として
産業用途
- 電子機器のプリント基板や電線、ケーブルなどの電気絶縁体、塗料やコーティング剤として
- 油火災などに効果的な発泡消火剤として
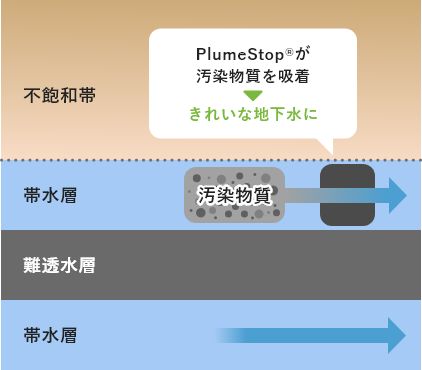
健康への影響
PFASは長期間環境中に残留し、生物の体内に蓄積しやすいという問題があります。これにより、以下のような健康影響が懸念されています。
- ガンのリスク増加: 一部のPFASは発がん性があるとされています。
- 免疫系への影響: 子どもの感染症に対する抵抗力が弱まる可能性があります。
- 内分泌系への影響: ホルモンバランスに悪影響を与える可能性があります。
PFAS規制(世界/日本)
EU:全PFASを500ng/L以下、複数PFASを100ng/L以下
2021年1月に「改正飲料水指令」の中で、全PFASを500ng/Lに、複数PFASを100ng/Lと規定しました。
※全PFASとは全てのPFASの総量。複数PFASは20種類のPFAS(PFOS・PFOAを含む)の総量
アメリカ合衆国:PFOSとPFOAを4ng/L以下、PFNAを1.0ng/L以下
2023年3月、6種類のPFASについてのMCL(最大許容濃度/日本の水道水質基準に相当)を、PFOSとPFOAを4ng/Lに、 PFHxS・PFNA・HFPO-DA(GenX Chemicals)を1.0ng/Lとする案を発表しました。この案は水質基準として2026年から法的拘束力を持って施行される予定です。
日本:50ng/L以下(暫定目標値)
2020年、水環境(地下水)や水道水の暫定目標値(PFOS及びPFOA)が決定されました。環境省が制定している水環境においては、水質の要監視項目に位置付けられて、暫定値ですが指針値50ng/lを設定しております。この要監視項目というのは、直ちに環境基準とはせず引き続き知見の集積に努めるものとしています。
厚生労働省が制定している水道水については、水質管理目標設定項目に位置付けられており、水環境と同様に暫定値として50ng/lとして設定されています。この水質管理目標設定値ですが、水道水中での検出の可能性があるなど、水質管理上留意する項目になります。
どちらも規制される基準の1歩手前となりますが、飲用井戸として利用している場合は、緊急的な対策として、井戸の利用の停止となります。
2021年4月: PFHxS(ペルフルオロヘキサンスルホン酸)が要検討項目に追加されました。
2024年2月: 2023年12月1日に改正された化審法施行令の一部が改正され、第一種特定化学物質にPFHxSが追加されました。
PFAS対応の変遷(世界/日本)
1940年頃から
PFAS(有機フッ素化合物)は、冷媒用のフロンガスの研究中にテトラフルオロエチレン(TFE)が重合してできたテフロンから始まります。1940年代から1950年代にかけて、テフロンは軍事産業や工業製品に広く使用されるようになり、1960年代には家庭用のフライパンなどにも普及しました。
撥水撥油剤、界面活性剤、半導体用反射防止剤、消火器の泡消火剤、殺虫剤等の幅広い用途に用いられました。導入当初は、人体への影響はなく、不活性であると考えられていました。
1990年代後半以降
1990年代後半になると、PFASによる環境汚染の問題が深刻に認識され始めました。1998年には、PFOSやPFOAを製造している企業の工場周辺住民に健康被害が頻発し、訴訟が起こる事態となりました。
2000年代に入ると、PFOSやPFOAの有害性が広く認識され、2009年にはストックホルム条約によりPFOSの製造・使用が国際的に制限されました。その後、2019年にはPFOAも同条約に追加され、規制が強化されました。
2006年
EPAとPFOS生産大手8社との間で合意が成立し、アメリカ国内では2000年比で2010年までに95%減、2015年までに全廃が決定しました。
EUでは、PFOSを含む製品の販売や輸入、使用については、EU域内で販売、輸入、使用が禁止されました。
2009年
日本では、2009年に化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)でPFOSが第一種特定化学物質に指定され、製造・輸入が原則禁止されました。
2021年以降
その後、2021年には環境省が全国の河川や地下水におけるPFAS汚染の実態を明らかにする調査結果を発表し、環境問題としての認識がさらに高まりました。
2023年にはPFHxS(ペルフルオロヘキサンスルホン酸)が化審法における第一種特定化学物質に指定され、製造・輸入・使用が原則禁止されました。これにより、日本国内でもPFASに対する規制が強化されています。








